・アノニマスさん
歴史的な決闘の多くは、あっという間に終わってしまったような気がします。
・アノニマスさん
本物のカタナで戦う人、誰も力を持たない人、パルクールで屋根を飛ぶ人を見に行くとき。
・アノニマスさん
これが現実だ、早く決断した方が勝ちだ、一手で戦局は変わる。
・アノニマスさん
誰かが言ったように、これは打撃と打撃の間が一瞬のことで、私もそう思います。
姿勢のひとつひとつに正確さを求めていることに感動しました、このビデオを紹介してくれてありがとう。
姿勢のひとつひとつに正確さを求めていることに感動しました、このビデオを紹介してくれてありがとう。
・アノニマスさん
超簡単に見えるんです。すごい技術
・アノニマスさん
封建時代に実際に行われたカタナの決闘が想像できる。負けた人は、前腕に冷たいものを感じてから、胸が切り裂かれたことに気づくのでしょうね。?
・アノニマスさん
アニメを見ていて、パッと終わってしまうのは、こういうことを見せようとしているのです。剣の時代の本当の決闘は、ほとんどが数秒で終わっていた。クレイジーな反応速度と長年の筋肉記憶
・アノニマスさん
x2倍速で見ると凄くよく見える
・アノニマスさん
複数人が絡むと手足が飛び散り、残酷で、素早く、血なまぐさい戦いになったことでしょう。
・アノニマスさん
動けないんです。彼らの精神的なプレッシャーは大変なものです。
出典元 https://www.youtube.com/watch?v=ndkh8MQw9ZM
にほんブログ村
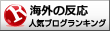
海外の反応ランキング


コメント
ただ現代の剣道をする人は手首を上げて右手と左手に重心を受け渡す打ち方をする人が多いが、動画を見ればわかるように、一刀流など実際の刀法では刀の重心はできるだけ動かさないで振る(手首を動かさず左手も上げる)ところが違う。その方が、力が常に一定にかかることと、剣先の動きが小さくなる。
これもあくまで型だし
現代的な剣道だと切っ先で当てても、斬ってないね。
え?池田屋は? 他にも幕末の多くの殺人事件は? 竜馬は抜かず拳銃撃ってたがw
以蔵が土佐から追い出されたきっかけの事件とかも刀同士の戦いだったはず。
戦国時代にも合戦の合間に平服での闘争があったはず。
平和な江戸時代でも辻斬りや忠臣蔵事件やら大老暗殺やら・・・みんな槍や弓や鉄砲持ってたの?
「戦い」にもいろいろあり、甲冑を着たときと平服のときとでは動きも適正な刀も違ってくる。
平服で戦う喧嘩なら甲冑の隙間を狙う必要はなく、当たればそれだけで戦闘力を奪える。
何を言ってるんだ? 昔は相撲か念力で戦ってたのか?
だからやむを得ず当てたあと力を前方に逃がす『打突』と言う動きになる。
古流の剣術は、全て真剣で戦うための技術。
当てるだけで致命傷にならない『打突』のような動きはない。
ついでに、竹刀よりはるかに重い真剣では、竹刀のように両手首の動きで素早く振る事は出来ない。
硬球用のバットで、剣道の小手・面の動きをしてみれば、大体真剣と同じくらいの手応えと速さになる。
程宗猷 「単刀法選」
日本刀法は神秘的だ。左右への変化がすさまじく誰にも予測できない。そのせいで槍を持ってしても毎回日本刀に負けてしまう。
屈大均「広東新語」
日本人が全力で動くとき風のように漂って動く。常に寡兵で陣に入って、たくさんの兵も抵抗できない。その刀の使い方は、長い方で構え守り、短いほうで止めを刺す。しゃがんでいるかのごとく低く移動し、決して退がらない。こちらが何人いようと対応される。日本列島の者だけの絶技である。
ビーム撃ち合ってた
コメントする